中国茶の道具「茶則」「茶通し」を竹を使ってDIYしてみた!
投稿日:2025年6月20日(金曜日)
こんにちは。フェリシモ女子DIY部のちまこです。
最近、家で中国茶を淹れて飲んでいます。茶道具を集めるのも楽しいです。
今回は中国茶の道具のひとつである「茶則(ちゃそく)」「茶通し(ちゃどおし)」を竹で作ってみたので、その様子をお伝えします。
下の写真の中央にある、竹素材のものが今回作った茶則と茶通しです!

茶則は、茶壺(ちゃふう)という中国茶用の小さな急須に茶葉を移す際に使用したり、茶葉の量を確認したり、状態を鑑賞したりするのに使います。
茶通しは茶針ともいいます。お茶を淹れる際に、茶壺の注ぎ口に詰まった茶葉を取り除くために使用する道具です。

知り合いのおうちに遊びに行った際に、所有している竹林に横たわっている竹がありました。許可をもらって少し切って分けてもらいました。

のこぎりで必要な分をカット。

節もあったので、のこぎりでカットしました。

長さは10cmほどにし、縦半分ぐらいに割りました。割ったときに小さく割れた方の竹を、もう少し細かく切って茶通しにすることにしました。

細く割った状態が上の写真です。いい感じに割れた竹が2本取れたので、茶通しは2本作ってみることにしました。
ここからの作業は、持って帰って後日行いました!

カッターを使って竹の鋭利な部分を面取りして、滑らかにしていきます。

仕上げに紙やすりで滑らかに整えていきます。
完成です!
細いのが「茶通し」で、大きい方が「茶則」です。

実際に使ってみた様子がこちら。
お茶の葉を茶則にのせておきます。お茶の葉を鑑賞したあと、小さな中国茶用の急須に茶葉を入れるのに使います。
中国茶は一緒に飲むお客さまと茶葉を眺めたり、味や香りを楽しんだりと、お茶を深く味わうことでリラックスやコミュニケーションツールにもなります。

茶通しを使うと、茶葉をスーッと入れていくことができます。

おうちにある茶器ともなじんで、いいものができました!
天然素材の道具があると、お茶の時間がより充実したものになりますね。
竹さえあれば簡単に作れます。
みなさまも中国茶にご興味があればぜひ作ってみてください!
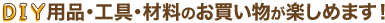




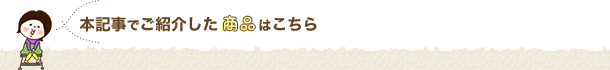

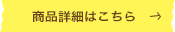



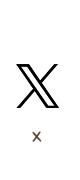





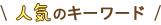

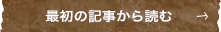
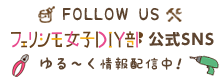









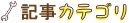
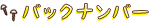





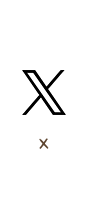
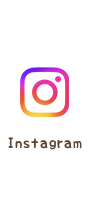



コメントはブログ管理者が公開するまで表示されません。