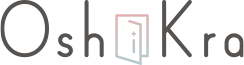小劇場の世界からしか生まれない新たな才能を信じて「劇作家・演出家 」のお仕事 ー瀬戸山 美咲さん(後編)ー【連載】推し事現場のあの仕事 #006
公開日 2022.11.04
わたしたちの“推し”が輝いている劇場やライブ会場などの“現場”。そこではふだんスポットライトを浴びることが少ない、多くの人々によって作品が作られています。本連載では、現場の裏側から作品を支えるさまざまなクリエイターたちに焦点を当て、現場でのモロモロや創作過程のエピソードなど、さまざまな“お仕事トーク”を深掘りしていきます。
第6回目のゲストは、演出家、劇作家、脚本家としてご活躍の瀬戸山 美咲(せとやま みさき)さん。ジャニーズメンバー出演舞台の演出や魅力的だと感じる俳優像についてうかがった〈前編〉に続き、〈後編〉では20代から30代初めの演劇活動に加え、少し意外なお仕事経験、ご自身の“推し”について語っていただきました(編集部)

瀬戸山 美咲さん
▼前編はこちら
俳優として魅力的なのは“嘘”がなくて“嘘”が上手い人 「劇作家・演出家」のお仕事 ー瀬戸山 美咲さん(前編)ー【連載】推し事現場のあの仕事 #006
――瀬戸山さんは大手主催の舞台から地方自治体とのコラボレーション、小劇場作品とさまざまな演劇シーンでご活躍ですが、プロとしてのスタートはご自身が主宰する劇団「ミナモザ」ですよね。
瀬戸山 2001年に「ミナモザ」を立ち上げました。旗揚げ当初から実際の事件や事故をベースにした作品を自分で書いて演出していましたが、当時はいわゆる社会派的な舞台があまり好意的に受け止められないことも多かったんです。俳優さんに出演をオファーしても「なんだか楽しくなさそう」ってお返事されて考え込んでしまう時期もありました。
――とても意外です。社会を映す事象が効果的に取り込まれ、かつエンタメとしても面白いのが瀬戸山さんの作品の特徴だと感じていますので。
瀬戸山 ありがとうございます。ですが、「ミナモザ」旗揚げからしばらくは道に迷いがちでした。それまでの作風と違うモードに挑戦しようとSF的な仕掛けを取り入れた作品を創ってみたこともあります。でも、自分が本当にやりたいのはドキュメンタリー的な要素としっかり向き合う演劇だろうと気づき、原点回帰のつもりで書いたのが2009年初演の『エモーショナルレイバー』(サンモールスタジオ)でした。
――『エモーショナルレイバー』は2011年にシアタートラム・ネクストジェネレーションの企画で再演版を拝見しましたが、マンションの一室で展開する振り込め詐欺グループの人間模様の描き方が日常的なのにソリッドで強く印象に残っています。
瀬戸山 『エモーショナルレイバー』は自分が30歳前後に書いた作品でもあり、当時のわたしの心象風景がかなり反映された戯曲だと思います。劇中の詐欺の電話の練習シーンは、それまで見てきた理不尽な演劇の稽古場をイメージして書きました。あの頃はプライベートもグチャグチャで大変な状況だったんです。初演の稽古初日の前日に大失恋をして朝方まで泣きはらして現場に行ったりもしました。そんなことがありつつ、男女の性差みたいなことも考えながら必死で創った作品です。
――まさかそんな状況で創られた作品だったとは!この『エモーショナルレイバー』再演で、「ミナモザ」と瀬戸山美咲さんのお名前が広く知られた印象もあります。
瀬戸山 だとしたらありがたいです。今思い出しても本当に大変な時期でした(笑)。


ミナモザ『エモーショナルレイバー』(撮影: 服部たかやす)
男性週刊誌やファッション誌のライターと演劇活動を両立させた日々
――瀬戸山さんは早稲田大学政経学部のご出身ですが、就職はなさらなかった?
瀬戸山 しなかったです。演劇といえば早稲田というイメージで、とにかく早稲田に行って演劇をやろうと高校生の時から決めていました。入学後に参加したゼミが政治思想史を専門にやるところで、周囲もまったく就職にがつがつしていない人ばかりだったこともあり、気づいたら就職先も決まらないまま卒業時期が見えてしまって。そこから「やっぱり演劇をやりたい!」と思い、動き始めました。
――ちょっと待ってください、そもそも演劇がやりたくて早稲田に入ったんですよね?
瀬戸山 勇気がなくてずっとやれていなくて……1年生の時に早大劇研のアトリエに話を聞きには行ったんですけど(笑)。大学在学中の3年間、舞台は観る専門で、4年生の時に「やっぱり芝居をやりたい!」と動き始めてからは裏方的なお手伝いをしたりしていました。
――大学卒業後はアルバイトをしながら本格的な演劇活動をスタート。
瀬戸山 当然、演劇で食べていけるはずもなく、保険会社のデータ入力をしたり、カフェで早朝から夕方までホールスタッフのアルバイトをして稽古に通っていました。
――「ミナモザ」の『彼らの敵』(2015年)駒場アゴラ劇場上演時のアフタートークでは、週刊誌のライターをなさっていたとお話されていましたね。
瀬戸山 演劇の稽古とアルバイトが続く生活の中で「書く仕事をしたい」と思うようになり、求人誌でライター事務所の募集を見て2社に応募したのが始まりです。1社はトレンド情報誌を作っているところで、そこは落ちました(笑)。受かったのが池袋にある男性週刊誌の記事を作る事務所で、芝居を続けながら1年くらいオジサンが読む週刊誌の取材記事を書いていました。
――当時のことも作品の種になっていると思いつつ、ハードそうなお仕事です。
瀬戸山 いろいろな場所に潜入取材にも行きました……詳しい内容は秘密にさせてください(笑)。記事を書いていたオジサン週刊誌は大手出版社が出していて、自分の担当編集者がたまたま大学時代の同期だったこともありました。そういう人に基本的な文章の書き方を教わって……。そうこうしているうちに、池袋の事務所が広告の仕事をメインで扱うようになり、雑誌をやり続けたい自分はフリーのライターとして活動を始めました。男性週刊誌でお付き合いのあった編集者さんが女性ファッション誌に異動したご縁もあって、ファッション誌でもライターとして記事を書きながら演劇を続ける日々でしたね。
――その時代にライターとしてジャニーズの取材もなさっていたんですよね。『グリーンマイル』加藤シゲアキさんとの対談インタビューで当時のエピソードを瀬戸山さんからうかがった時は驚きました!
瀬戸山 わたしもフリーライター時代に取材をさせていただいた加藤さん主演の舞台で自分が演出をする日が来るとは思ってもいませんでした。人生、何が起きるか本当にわからないです。
ライターをやめ、演劇だけと向き合おうと決めたきっかけ
――そして演劇とフリーライターの両輪で活動する中、ひとつの転機が。
瀬戸山 ある時期から雑誌の記事を書く気力がなくなってしまったんです。
――きっかけをうかがってもいいですか?
瀬戸山 2011年の東日本大震災です。当時はライターとして被災地に取材に行く機会も多く、自分がその仕事をする意味も感じていました。でも、世の中が落ち着き始めた頃から雑誌も次第に平常運転に戻り、わたしのところに依頼が来る記事も“モテるテクニック”や“結婚”みたいな内容のものが多くなって、次第にそういう記事を上手く書くことができなくなったんです。自分が興味を持てなくなってしまったのが大きな理由ですが、ちょうどその頃、それまで組んでいた編集者さんが異動になったことも影響していると思います。

ライター時代の1枚 撮影: 初沢亜利
――ライターにとって編集さんとの関係って大きいですから。
瀬戸山 そうなんです。それまではファッション誌でも少し硬派というか、女性の生き方みたいな記事も書かせてもらっていたのですが、体制が変わって、“モテテク”的な方向性の記事を書くよう依頼されて執筆した時に新しい編集さんから「良くないですね」ってバッサリ斬られて。自分でもその雑誌が求めるものを書けているとは思えなかったので、次第にファッション誌などの仕事からはフェードアウトして、単行本を作る手伝いをしたりしていました。
――2011年は『エモーショナルレイバー』で広く注目され、震災があって意識が変わり……いろいろな意味で瀬戸山さんにとって転機の年。
瀬戸山 今、振り返るとそうですね。その後、2013年頃にライターの仕事からは離れ、演劇活動だけに気持ちを向けるようになりました。
――当たり前の質問になってしまいますが、やはり演劇で食べていくのは大変ですか?
瀬戸山 わたしの場合はめちゃくちゃ大変でした(笑)。自分が劇団の主宰ということもあり、公演を1本打つごとにそこそこの借金ができて、それをフリーライターの仕事で少しずつ返すという状況が続きましたし。まったく手もとにお金がない時は、翌日の取材の交通費をねん出するために、自宅内にある最後の本をブックオフに売りに行ったりもしていました。30代の初めくらいまでは本当にお金がなくて、綱渡りの生活が続いたと思います。

――今、劇団で演劇をやっている若い世代には特に厳しい状況が続いています。
瀬戸山 それはもう間違いないです。コロナ禍で公演が中止されると、舞台を上演できていないにもかかわらず、借金だけ背負うようなこともありますから。今は若い劇作家や演出家が安定した環境で作品を創れる現場がとても少ないと実感します。でも、わたしは「ミナモザ」の公演を打ってきたことが自分の糧になっていると信じていますし、小劇場の世界からしか生まれない新たな才能があると思っています。いろいろ厳しい状況で、やる気だけではどうにもならない時代になってしまったこともあり、彼らの活動への支援が必要だと強く感じます。
会長をやらせてもらっている日本劇作家協会では、少しでも機会の創出になればと考え、若手の劇作家会費を免除する奨学金制度を設けました。若い人たちへの情報が遮断されたり、先輩作家との交流がなくなってしまうことを避けたかったんです。
――ありがとうございます!最後にご自身の“推し”について語っていただけますか。
瀬戸山 “推し”と言っていいのかドキドキですが、アーティスト・三浦大知さんを尊敬しています。「Who’s The Man」という曲のMVを観た時に衝撃を受け、後からそれ以前の作品も拝聴し、ライブなどにもうかがっています。ライブを拝見するたびにダンスと歌、その両方のクオリティの高さに心打たれますし、ステージングも凝っていてとにかくカッコいいんです!演劇とは違う分野でご活躍のパフォーマー、クリエイターとして刺激をいただく存在ですね。

【取材note】
現場で取材をしていながらも「演出家=演出する人」と緩やかに認識していた自分に喝が入ったインタビューでした。瀬戸山さんをはじめ、演出家によっては企画段階から深く作品にかかわり、稽古場や劇場以外の場所でも創る作業を続けている。演劇は長い長い時間をかけ、不確かな要素の中、繊細に丁寧に紡がれていくものなのだとあらためて実感しています。先が見えないこの時代に舞台上で生まれる熱とそれが客席に届くことを信じ、作品を創り続ける人たちが確かにそこにいる……。
OshiKra『推し事現場のあの仕事』ではこれまで12回にわたり、7名のプレイヤー、クリエイター、劇場関係者それぞれに長時間にわたってお話をうかがってきました。こと舞台関係のインタビューは作品プロモーションがメインになることも多い中、今の仕事に就くきっかけやコロナ禍での現場ピソードなど、ゲストの皆さまがストレートにお話しくださったことで、わたしたち観客も新たな視点を得られたと思っています。取材にご協力いただきました皆さま、神戸の地より舵取りとサポートをおこなってくださった編集部の方々、そして本連載をお読みいただき、SNS等でアツい感想をお寄せくださった読者の皆さま……本当にありがとうございました。
さあ、わたしたちの“現場”でこれからも“推し”の輝きを見つめていきましょう!
(取材・文・撮影=上村由紀子)