#06 [2024/03.11]
せんぱいたちの、このごろ
どれだけキャリアや年齢が上がっても、
何もできなかったころの自分に
寄り添う気持ちを忘れたくないです。
川口雄大さんYuta Kawaguchi


こう語るのは、東京の映画会社を退職し、2024年3月から人材会社の人事職に転職した川口雄大さん、29歳だ。
会ったことはないけれど、なぜか魅力を感じる人っていないだろうか。
私にとって、川口さんは長年そういった存在だった。
これまで、彼がSNSで発信する写真や言葉、映画や小説のレビューに幾度となく心を奪われてきた私。
今回、念願かなってやっと直接お会いすることができた。
取材の依頼をすると「それだったら一緒に山に登りませんか?」というユニークな返信をしてくれるような人。
彼の持つ哲学は、きっと悩める新社会人の小さな光になるはずだ。取材を終えたあと、私は確かにそう思った。
写真がきっかけで開かれていった
カルチャーの世界
川口さん:大学に入るまでは、流されるままに生きていたような気がします。兄と弟につられ、なんとなくサッカーは続けていましたけど、そこまで好きではなかったですし、勉強もあまり得意ではなかったです。
そんな川口さんが初めて自分からのめり込んだのは、写真を撮ること。そのきっかけはとてもひょんなことからだった。
川口さん:昔デコログってあったじゃないですか。高校3年のある日、なんてことない地元の河川敷で撮った写真をデコログに投稿したら、知らない誰かが写真を褒めてくれて。それがすごく嬉しかったんです。自分の意思でやったことが初めて誰かに認められる経験だった気がします。
その後、祖母にねだってカメラを買ってもらい、大学では写真部に所属した川口さん。写真を好きになったことが入り口で、カルチャー全体への興味がどんどん開かれていったそう。

とてもにこやかに話されているのは、K-POPアイドルグループtwiceのこと。
この日は新曲発売日で、その感動的な歌詞の良さについて熱弁中。
川口さん:写真が好きになると自分の好きな写真家さんができると思いますが、僕はそれが奥山由之さんでした。奥山さんが好きになったら今度はファッション雑誌を好きになって、ファッション雑誌を読んでいたら今度は映画のことが好きになる……そんな連鎖で、気づけばカルチャー全体に関心が向くようになっていました。
しかし、ファーストキャリアではカルチャーとは一切関係のない求人広告会社の営業職に就くことを決めた。
川口さん:出版社にも内定をいただいたのですが、僕のやりたい仕事ができるまでには下積みが10年ぐらい必要だったこともあり、ファーストキャリアはお給料もよくて都会のきれいなビルの中にある広告会社を選びました(笑)。
毎日数字に追われる生活。
ここで自分の居場所を確立するには?
新卒1年目は数字に追われる毎日で、回し車の中のハムスターのようだったと振り返る川口さん。
川口さん:毎週末、一人ひとりの売り上げ達成率と順位が配られるんですよ。闘争心がほぼない私にとって、そこに自分の価値基準を置かれるのはすごく苦しかったです。成績は悪いわけではないけど、すごくよいわけでもない。このままいけば、2年目以降この会社で自分の居場所はなくなると思いました。
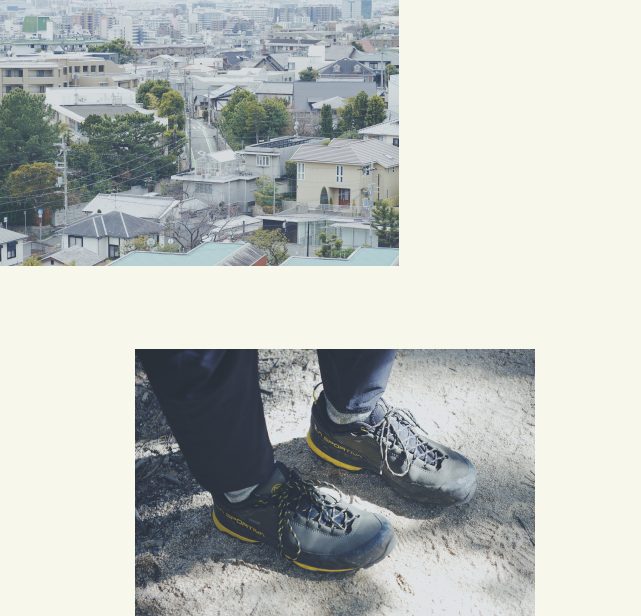
下:スポルティバというイタリアのブランドの登山靴。
山小屋で出会った友人に教えてもらい、下山後すぐ購入。
そんな危機感が迫り、数字ではない、人と違うよさを発揮できる方法がないかを考えたとき、また大好きなカルチャーへと立ち返ったそう。
川口さん:会社の毎日のルーティーンの中に、朝礼で自分の興味を持ったニュースを10人前後のチームで発表する場があったんです。基本的には日経新聞から共有したいニュースやそれについて感じたことを発表するのですが、私はそこで政治的なことを絡めながら、大好きな映画のことを中心に発表するようにしました。もちろんめちゃくちゃ勉強もして。
するとだんだん、会社の仕事や責任によって生まれる居場所ではなく、自分の好きな映画によって居場所が確立されていったという。
川口さん:本当に映画の話ばかりしていました(笑)。どんな場所でも自分の内側から湧き出るもので居場所を形成していくことが大事なんだと気付かされました。新卒から4年働いたとき、先輩から「そんなに映画が好きなら映画の仕事に挑戦してみたら?」と背中を押され、映画会社へ転職することを決めました。
好きなことを仕事にしたからこそ
見えてきたこと
映画会社では映画の宣伝業務を担当していた川口さん。そこでもファーストキャリアで得た居場所づくりの方法が役に立ったという。
川口さん:週に1回、取引先に一斉に送信するおすすめ映画のメルマガを独自で作成していました。もちろん仕事につなげるためというのはありましたが、半分は映画が好きでめちゃくちゃ詳しい人だと分かってもらいたくて。
居心地のいい居場所をつくったり、よい仕事をしていくためには、まずは自己開示することが重要だと考えてのことだった。そんな日々を2年送るなかで、自分は映画の評論が好きなんだと気づいた川口さん。
川口さん:仕事はめちゃくちゃ楽しかったですけど、映画は仕事じゃなくてもずっと関わっていけるし、一旦ここまででいいかなと。映画会社としての映画の愛し方と私の映画への愛はちょっと違うことが働いてみて分かりました。
人とじっくり向き合った山小屋での生活。
次に進む方向がおのずと見えた
求人広告の営業から映画会社の宣伝。6年間突っ走ってきた川口さんは、1年間の小休止期間を設け、ふだん経験できないことをやろうと決意。向かった先は北アルプス、双六岳の山小屋だった。
川口さん:単純すぎるのですが、昔から漠然と山が好きだったことと、人と話すことが好きなことをかけ合わせると、「山、接客業」で山小屋でのバイトかな、と(笑)。実際に働いてみると登山道の整備やセメント作りのような、接客だけする仕事ではなかったんですけど、それでも自分の得意なことに改めて気づける期間だったなと思います。

除雪と凍っている道の点検をしている様子だそう。
山小屋を訪れた登山客がいい滞在だったと思って帰れるよう、一緒に働く仲間と毎日密なコミュニケーションを取ったり、登山客と楽しく会話をしたり。人とじっくり向き合うことが得意だと分かった川口さん。半年間の山小屋生活を終え、次のステージをたくさんの人の話を聞くことのできる人材会社の人事職に決めた。
いつでも
か弱い一個人の側に立てる人間でいたい。
そのために私は学ぶことを止めない
最後に今後の目標を問うと、「こうなりたいはないけど、こうなりたくはないという姿は明確にありますね」と話てくれた。
川口さん:どれだけキャリアや年齢が上がっても、何もできなかったころの自分に寄り添う気持ちを忘れたくないです。それこそ、これから私は新卒くらいのみなさんとたくさん関わっていくと思うのですが、会社やシステム側だけに立ってしまうとこぼれ落ちてしまうものが絶対にあって。私はいつも、か弱い一個人の側に立てる人間でいたいです。
でもこれって、やっぱり日々勉強なんですよね。インプットを止めると想像力は欠如していく。できることが増えるとサボってしまいそうになりますが、学びを止めず、いろんなところに想像力が及ぶ人間でいたいです。
果たして私は、これまでどんなふうにして自分の居場所を形成してきただろうか。大人になるにつれ、自分の内側にあるものよりも、責任や地位の確立のため、周りに期待されている自分の役割を見つけることを優先してきたように思う。
そんな姿の自分も嫌いではないけれど、より心地よい居場所をつくるため、もう少し自分の心を中心にした社会とのかかわり方を見つけていきたい。その場の空気に染まりすぎず、自分の軸を保つことは、心に余裕という隙間をつくり、結果的に周囲の人にも気を配れるようになるのかもしれない。川口さんからそんなことを教わった。
そんな川口さんから、オススメの一冊
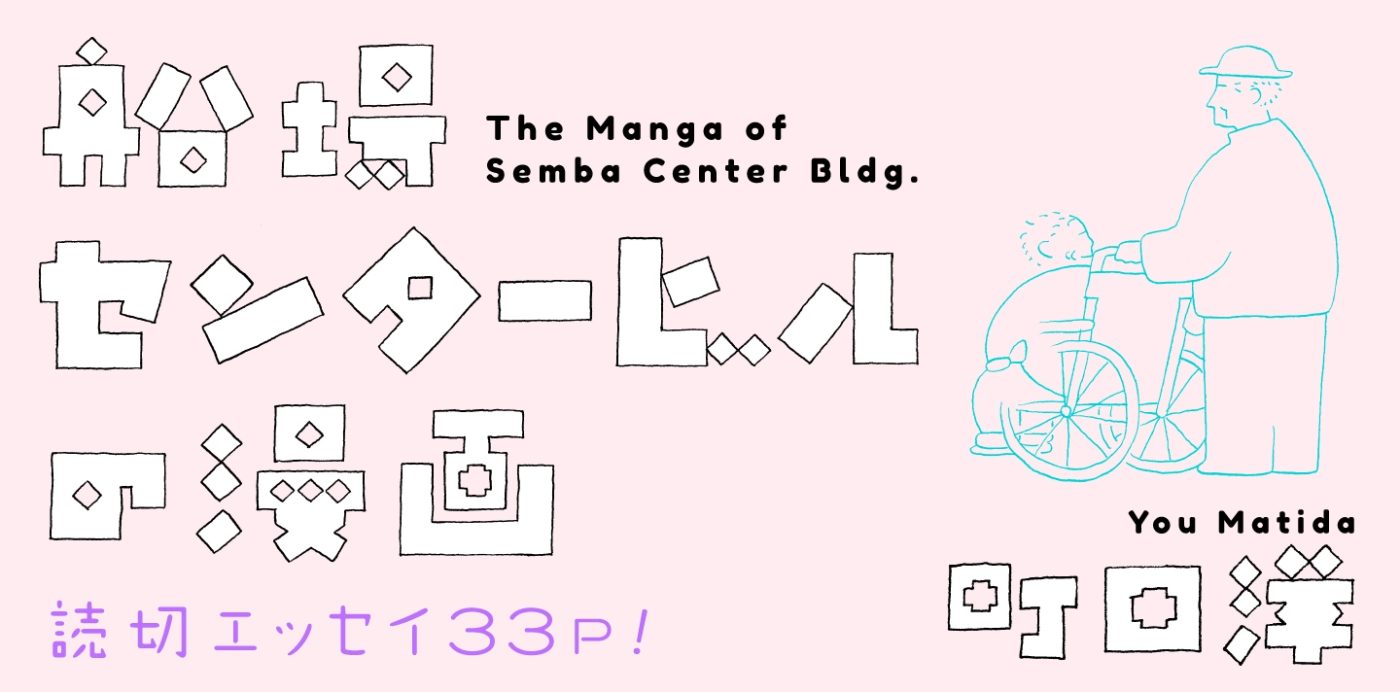
『船場センタービルの漫画』©︎町田洋/トーチweb
▲画像クリックで読むことができます▲
川口さん:船場センタービルの50周年を記念して制作された物語です。悩んだときにいつも立ち返る本になっています。自分が存在する理由って自分の中だけにあるのではなくて、社会、他者とのあいだにいる自分の中にあるもの。考えてみれば当たり前のことなのですが、それを改めて確認できる物語です。
テーマは「鬱」ですが、とてもポップでキュートに描かれているので、疲れたときにぜひ読んでみてください。
STAFF
photo / text : Nana Nose




