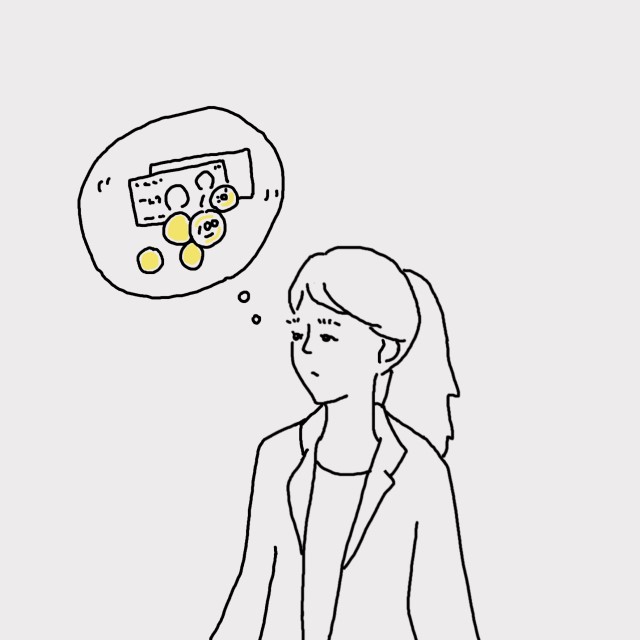ついお金を使っちゃう。
ティップス
もしかして浪費癖あるかも……。
若いうちに改善するには?
社会人になり、学生時代と比べて大きな金額の給与をもらうようになったことで、浪費癖に悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。
「浪費癖は治せない」という人もいますが、わたしは改善できるのではないかと考えています。
そこでこの記事では、浪費の原因として考えられること、浪費癖を改善するために心がけたいことをご紹介していきます。
浪費癖をなんとかしたい!

まず、浪費とはどういう意味でしょうか?
辞書を見ると「金銭・物・精力などを無駄遣いすること」とあります。
これは「将来の利益のために多額の金銭を投入する」投資や「家賃や食費など生活に必要なものに出費する」消費とは、明確に異なるものです。
その上で浪費癖(ろうひへき)とは「金銭などをやたらにどんどん使ってしまう習性」を指します。
具体的な数的基準や統計はないようですが、浪費癖の特徴としては次のようなものが挙げられます。
浪費癖の特徴とは?
☑ お金があったらすぐに使ってしまう
☑ 銀行口座の残高やクレジットカードの支払額が分からない
☑ カード明細を見ても何にお金を使ったか思い出せない
☑ 感情に左右されやすく、ストレス発散で買い物する
☑ 「今だけ」「限定」という言葉に弱い
☑ 「お金は使わないと損」と思いやすい
浪費癖は決して珍しいことではありませんが、「老後4000万円問題」などが唱えられる今、貯金ができていない現状に不安を感じている方もたくさんいることでしょう。
その不安、とてもよく分かります……。
不安を解消するために、まずは一緒に浪費の原因を考えることから始めてみませんか?
つい浪費してしまうのはなぜ?
原因と向き合おう
物欲が強いから
浪費癖の代表的な原因として、物事に対して強い欲求がある場合が考えられます。例えば、おしゃれが大好きな人は、洋服や靴、アクセサリーをたくさん手に入れたいと思うことでしょう。そのため、結果的に多額のお金を使う癖がついてしまうのです。また、限定商品やセールに弱い人は「今しか買えない」と思うと飛びついてしまうことも。
貯金に関心がないから
浪費癖と聞くと、収入の少ない人が「金欠だ」と言って困っている様子が目に浮かぶかもしれません。でも、収入が多くても「今が楽しいのがいちばん」「宵越しの金は持たない」と考えている人の場合、貯金に無頓着で、手もとにある分だけお金を使ってしまう傾向があるようです。
計画性がないから
高級ブランド品を大量に購入したりする人に見られる理由です。そういった行動は本来、収入と支出のバランスを考えて判断するもの。しかし、浪費癖のある人は、目先のことしか考えていないので「なんとかなるでしょう」と解釈してしまうみたいです。
買いものは快楽を感じる行為だから
買いものをする際、脳では幸福ホルモンである「ドーパミン」が分泌されているそうです。つまり、買いものは快楽を伴う行為なのです。そのため、過度のストレスを発散させる手段として浪費をしてしまう場合もあります。人によっては、経済観念のない買いものを長期間に渡って繰り返し「買いもの中毒」になってしまう場合も少なくないのだとか……。
なんとなくお金を使っているから
仕事帰り、特に用事もないのに、コンビニエンスストアに立ち寄ってしまう方はいませんか?他にも、外食やデリバリーが好きで、毎日のように利用している方もいるかもしれません。1回ごとの使用額は少なくても、積み重ねることで習慣になり、浪費癖に結びついてしまいます。
ついネットショッピングしてしまうから
ついついネットショッピングしてしまうのは、在宅・スマホ時代ならではの浪費パターン。家にいる時間が長いとネットで買い物を済ませ、ついでに買いすぎてしまうケースも少なくありません。すごく必要というわけではないのに、「とりあえずカートに入れる」という行動が習慣になってしまっている人も多いです。
小さな“ご褒美”がエスカレートしているから
最初は週1だったご褒美スイーツが、気づけば毎日に。そんな自分への日常の小さなご褒美がエスカレートしてしまうと、1回の出費は少なくても月全体の支出はふくらんでしまいます。日ごろの習慣化が浪費癖の温床になってしまうこともあるため注意しなければなりません。
無理をせずに改善していく方法

最後に、無理せず浪費癖を改善していく方法をご紹介します。
家計簿をつける
浪費癖のある人は、自分の収支を把握していない場合が多いです。まずは家計簿をつけてみましょう。記録することで、いつ何にいくら使ったのか、どんなことにお金をよく使っているのかが客観的に分かります。慣れてきたら、1ヵ月の予算を決めた上で、その範囲に収まるように生活するのもよいでしょう。
それに加え、わたしの場合は、家賃やカードの支払い、事前に分かっている支出を月初に記載し「今月はこれだけ生活費がかかるから他のところは抑えよう」といった判断をするようにしています。
キャッシュレス決済を使わない
現金を手もとに準備する必要がなく、決済することでポイントも貯まるキャッシュレス決済は、すっかり一般に普及しました。ただ、現金と比べてお金を使っている感覚が薄いため「つい使い過ぎてしまう」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、キャッシュレス決済を使わないようにするのもおすすめです。とはいえ、完全に禁止してしまうと不便なので、まずは「1週間に1回」のように、ゆるいペースから挑戦してみましょう。
お金を使わない趣味を探す
この世界は、お金を必要とするアクティビティで満ちています。そういった物事はもちろん刺激的で楽しいのですが、そればかりでは、お金を使わないと幸福を感じられないようになってしまうかも。
そこで、散歩や図書館での読書といった、お金を使わない趣味を探してみるのもよいのではないでしょうか。特に運動は、ストレス解消や睡眠の質の向上といったメリットがありますよ。
予算を“がんばらない範囲”でゆるく決める
浪費癖を改善するには計画的にお金を使えるよう、予算を設定するのも効果的です。「食費は毎月●円まで」など、だいたいの予算を決めておけば浪費を防げます。
ただし、予算の設定金額は“がんばらない範囲”にすることが重要です。あまり無理に切り詰めすぎるとストレスが溜まって衝動買いしてしまう恐れがあります。その反面、無理のない設定ならストレスが溜まりにくく、“目標を達成できた感”を味わいやすくなりますよ。
買い物前に「5秒だけ考える」習慣をつくる
ついつい買いすぎてしまう人や、衝動買いをしがちな人は、買い物前に「5秒だけ考える」習慣をつくりましょう。
どんなに欲しいと思ったものでも、買い物かごにすぐ入れてしまったり、レジに直行してしまうのはNG。「これは本当に必要?」「今買わないと困る?」など、自分に対して5秒問いかけてみると気持ちが冷静になり、浪費を抑えられます。
小さな“達成感”を自分にプレゼントする
浪費癖を改善するためには、ただ我慢するだけでなく、“お金のやりくり=楽しい”という印象を強化させることも重要なポイントです。
たとえば「1週間、予算内でお金を使う記録が続いたらお気に入りのコーヒーを飲む」など、目標を達成したときにささやかな自分へのご褒美を与えれば楽しみながらお金をやりくりできるようになるでしょう。
それって本当に浪費?
必要な支出との違いとは
ちなみに、お金を使うこと=浪費というわけではありません。
冒頭でも説明した通り、浪費とは金銭・物・精力などを無駄遣いすることです。何でも我慢すること=正解とは限りません。「必要なものを買ったり、心が豊かになったりするための支出は浪費ではない」とわたしは考えます。
もちろん使いすぎはNGですが、あまり自分に厳しくしすぎず無理のない節約を心がけましょう。
浪費癖の原因と改善策について見てきましたが、何か参考になる部分はありましたか?
浪費癖は一朝一夕で改善できるものではありません。
「浪費癖を何とかしたい!」と思っている方はぜひ、今日から対策していきましょう。
STAFF
text:Kamiya Sayoko、mishima
illustration:lilyco