『あたらしい日々への短歌賞』
受賞短歌発表
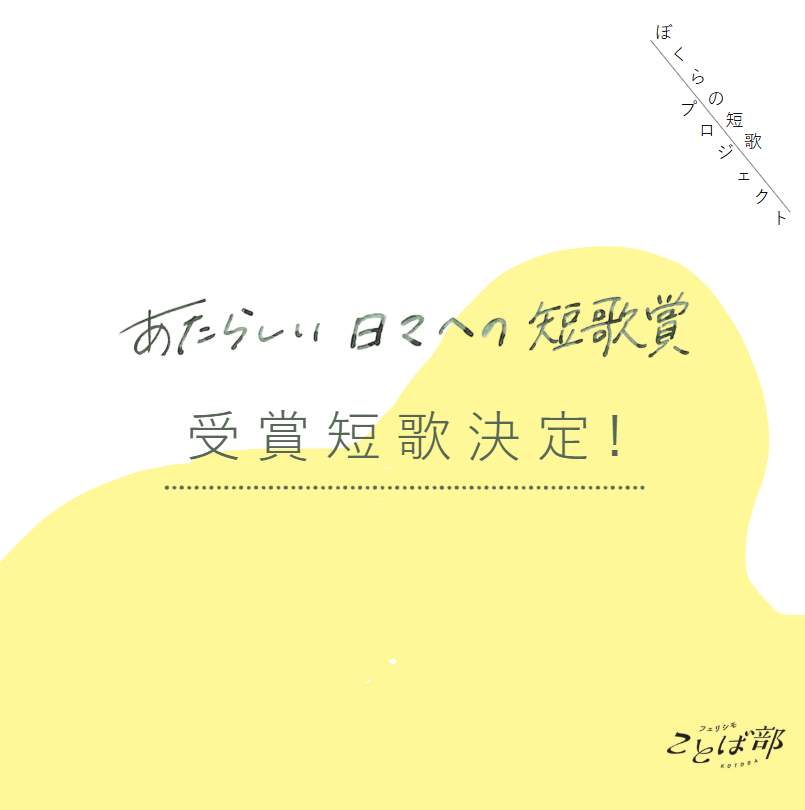
こんにちは、ことば部部長のやまぐちです。
3月17日(月)からの1ヶ月間募集させていただいた『あたらしい日々への短歌賞』、受賞短歌を発表いたします。
今回の短歌賞では、323名から812首のご応募をいただきました。
審査員の木下龍也さんにはご応募いただいた全ての短歌にお目通しいただき、その中から金賞・銀賞・銅賞の6首を選首いただきました。
(今回佳作も9首、選首いただいております。そちらについては後日発表させていただきます。)
改めて、今回はご応募いただき、ありがとうございました。
選ばれた短歌を木下さんの選評とともに、ご確認ください。
〈金賞〉1名
段ボールもうしめちゃったよ紙袋いっぱいの愛を抱いて上京
名前:ひらがな
審査員コメント:〝段ボール〟は業者の方に預けるだけの状態。手荷物は最小限にしてある。なのに、あれもこれもと色んなものを渡されて結局、〝紙袋いっぱい〟になる。渡す人としては、主体を心配する気持ちから、東京で役に立ちそうなもの、道中で食べてほしいものなど、ぎりぎりになってもどんどん思いついてしまうのだ。それらをまとめ、名前をつけるとしたら紛れもなく〝愛〟だろう。その〝愛〟の質量を主体は腕に感じながらあたらしい日々へと向かう。字余りの〝よ〟がこれまでの日々とこれからの日々を途切れることなく、地続きに繋いでくれている。
〈銀賞〉2名
カラオケでしわくちゃになる表情を見ていた 見せてくれていたから
名前:植垣颯希
審査員コメント: なりふり構わない全力の歌唱、とびきりの笑顔、ぐちゃぐちゃの泣き顔。主体の目に映っていたのはどんな〝表情〟だろう。どの可能性もあるが、おそらくそれは心を許している人にしか見せない〝表情〟だ。〝見ていた〟と〝見せてくれていた〟を〝見ている〟と〝見せてくれている〟に変えても成立するこの歌が回想として書かれているのは、その場では〝見せてくれてい〟ることに気が付かなかったからかもしれない。一字空けも時間的な距離を表しているはずだ。振り返ってみれば、あの人はかけがえのない存在だった、ということをあたらしい日々のなかでひとり、ひしひしと感じている。そんな切ない歌として僕は読んだ。
アイロンがけの丁寧なハンカチを嗅ぐそれで帰れる町並みがある
名前:薄暑なつ
審査員コメント:洗剤や柔軟剤の匂いでも、布の匂いでもなく、〝丁寧〟に〝アイロンがけ〟をした〝ハンカチ〟独特の匂いが確かにある。それを〝嗅ぐ〟ことで、離れていても、まるでそこにいるかのように〝町並みが〟目に浮かぶという一首。〝ハンカチ〟に〝アイロンがけ〟をしてくれたのがその〝町並み〟にいる人なのだとしたら、主体はその〝ハンカチを〟通常の用途では使わず、思い出すためのお守りとして持ち歩いているのだろう。匂いはいつまでも続かないが、きっと大丈夫。〝町並み〟のその人がしてくれたように、自分も〝アイロンがけ〟を〝丁寧〟にすれば、その〝ハンカチ〟や別の〝ハンカチ〟に独特の匂いを宿し、お守りを引き継ぐことができるのだから。いつまでも、いつでも帰れるのだ。
〈銅賞〉3名
電話すらとれない僕の図体は東京タワーからは見えない
名前:りきなが
審査員コメント:〝電話〟対応は新入社員に任されることが多い。が、〝僕〟は呼出音に反応できず、他の社員が対応している。上手に受け答えができない、ですらないため、オフィスで変に目立ってしまっているような気がする。その感覚を表すために〝図体〟という大きな身体を指す場合の多い言葉が選ばれているだろう。あるいは、実際に大きいのに役に立てないという焦りか。そんなとき、窓から〝東京タワー〟が〝見え〟る。あそこに立てば、こんな自分も風景の一部というか、視認できないほど小さいじゃないか。そんなふうに泡立つ心を抑えているのかもしれない。ありがちな比較対象としては宇宙だと思うが、〝東京タワー〟は思いも寄らなかった。
ビンゴカード開けるみたいに新品の手帳にいくつかたのしい予定
名前:野崎凪
審査員コメント:見開きのページに一箇月分の予定を記載できるマンスリータイプの〝手帳〟。使い始めは真っ白だが、〝予定〟が入るごとにひとつひとつの枡目が埋まっていく。その様子を〝ビンゴ〟に喩えた歌。〝いくつかたのしい予定〟として〝開け〟た穴があれば、〝予定〟のない空白の日や〝たのしい〟と思えそうにない〝予定〟の日さえ、ゲームのわくわくを高めてくれる枡目となる。「ビンゴ!」と叫べる月も叫べない月もあるだろう。それでも日々を待ち遠しくさせてくれる見事な比喩だと思う。〝ビンゴ〟は複数人が参加するゲームだ。もしかしたら、隣の席の人も、向かいの席の人も、それぞれの 〝カード 〟を見つめながら、明日を待っているのかもしれない。
春風にあと押しされて洗剤でだけ知っている花を育てる
名前:鈴城戸
審査員コメント:ピオニーの香りは香料として〝知っている〟が、芍薬を〝育て〟たことはない。マグノリアの姿はパッケージのイラストとして〝知っている〟が、木蓮を〝育て〟たことはない。〝育て〟てみれば、〝洗剤〟のそれとはまったく違うかもしれないし、かなり似ているかもしれない。香料と実際の香り、イラストと実際の姿、どちらに価値があるかを確かめるために〝育てる〟わけではない。〝育て〟てみなければ、香料のみ、イラストのみを知っている自分のままなのだ。だから〝育てる〟。あたらしい日々を始める相棒としてうってつけな〝春風〟とともに。他者にはわからないほどささやかな、けれど、主体にとっては大きな変化への一歩だ。
〈審査員〉
木下龍也さん

1988年生まれ。歌人。歌集は『つむじ風、ここにあります』『きみを嫌いな奴はクズだよ』『オールアラウンドユー』『あなたのための短歌集』。その他、短歌入門書『天才による凡人のための短歌教室』や谷川俊太郎との共著『これより先には入れません』など著書多数。近刊は『すごい短歌部』。2025年4月よりNHK Eテレ「NHK短歌」選者。
X:(@kino112)>> https://x.com/kino112
